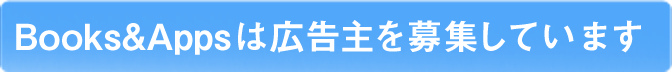従業員を一定の価値観に染めようとする会社は数多くある。例えば、「ビジョナリー・カンパニー」というベストセラーは長く繁栄し、存続する会社、例えば3M、フォード、GE、ジョンソン&ジョンソン、ウォルマートなどの業界の重鎮企業を取り上げ、従業員を一定の価値観に染め上げたほうが強い組織が作れる、という主張を展開している。
従業員を一定の価値観に染めようとする会社は数多くある。例えば、「ビジョナリー・カンパニー」というベストセラーは長く繁栄し、存続する会社、例えば3M、フォード、GE、ジョンソン&ジョンソン、ウォルマートなどの業界の重鎮企業を取り上げ、従業員を一定の価値観に染め上げたほうが強い組織が作れる、という主張を展開している。
ある意味これは正しい。現代において最も強い組織の一つである宗教団体は、構成員が単一もしくはそれに近い価値観を共有しているため、非常に強固であり、時代を超えて存続する可能性が高い。事実、「キリスト教」を始めとする世界宗教の多くは千年単位で存続している。
しかし現在、実際に多くの会社をまわってみると、必ずしも強い組織は「経営陣による従業員への価値観の押し付け」を推奨しているわけではないと感じる。うまくいくのは、「コントロールをできるだけ排除」した企業群だ。
とくにここ5~6年の間に成果をあげている新興企業においてはその傾向は顕著だと思う。
また、私が昔訪れた香料会社でも、その研究部門は「企業の業績」を気にせずとも働ける環境が提供されていた。営業や工場は眉をひそめていたが。
これは一体どういうことだろうか。現代の企業における最大の資源である「知識労働者」を研究していたピーター・ドラッカーは著作「新しい現実」においてこのように述べている。
”彼ら(知識労働者)にとって大切なことは、自分の会社、病院、美術館ではない。大切なことは、プロの仕事がどうかである。
彼らとしても、自らの専門能力を雇用主たる組織の目的、ニーズ、条件に合わせなければならないということは知っている。多かれ少なかれ、そのことは受け入れている。しかしそれらのことは、彼らにとってますます二義的となっている。
知識労働者の価値体系からずれば、組織の価値観は二の次である。専門分野において優れた成績を上げるには、組織の価値観などは障害にすぎないかもしれない。”
経営者にとってみれば、「価値観の統一された集団」を扱うほうが経営ははるかに楽である。
しかし、「知識労働者」にとってみれば、そういったことは瑣末なことにすぎない。率直に言えば、「どうでもいい話」なのである。
ドラッカーはつづけてこう述べる。
”日本では、とくに企業に働く古い世代の人達には想像さえできない問題にちがいない。しかし、日本においても変化は不可避である。なぜなら、それは知識の本質に由来する問題だからである”
アメリカにおいてはすでに2000年代の初頭にこの問題が顕著であった。
”ここから、やがてあらゆる先進国が直面することになる問題、アメリカではすでに現実のものとなっている問題が出てくる。すなわち、組織としての競争力維持のために必要とされる経済的な業績に対する献身を、いかに確保するかという問題である。”
「知識労働者」は、本質的に自分の属する組織の業績に興味はない。また、そういった業績に興味を持つよりも、専門分野に真剣に取り組んだほうが、優れた仕事ができる。
高度な仕事を労働者に求めれば求めるほど、「企業の都合」にその仕事内容を合わせるわけには行かなくなる。「知識」というものは、その応用分野が広ければ広いほど価値があるからだ。そこにジレンマが存在する。
「知識労働」を目指す企業であれば、そのバランスをどのように取っていくのか、創意工夫が求められる。