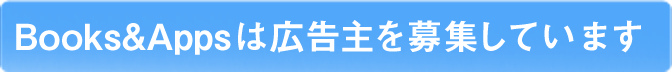つい先日、日経新聞に「餃子の王将」に関する記事が出た。”汗と涙、挫折…「餃子の王将」スパルタ研修ルポ”というタイトルなのだが、ああ、今年もこれが話題になる季節になったか、という、もはや風物詩のレベルである。
つい先日、日経新聞に「餃子の王将」に関する記事が出た。”汗と涙、挫折…「餃子の王将」スパルタ研修ルポ”というタイトルなのだが、ああ、今年もこれが話題になる季節になったか、という、もはや風物詩のレベルである。
テレビでもよく取り上げられているので、ご存じの方も多いと思うが、「大声を出させたり」「社訓を暗証させたり」「夜通し走らせたり」「理不尽に怒鳴りつけたり」と、新人を精神的に追い込むような状況をたくさん与え、合宿の終わりにはそれをクリアした「達成感」を味わわせる研修である。
そういった研修を一般的に(?)スパルタ研修と言うそうだが、これについては賛否両論である。
合理的だ、という主張する方々の意見はほとんど以下のようなものである。
記事を引用すれば
”「外食は就職セミナーにブースを出しても就活生は並ばない。ふるいにかけられた学生がやってくる。そういう世界です。厳しい研修で学生から社会人へ気持ちを完全に切り替えてもらう。辞令だけでは変わらない。厳しい研修を乗り越えられるから、店舗で苦しい局面にも打ち勝てる」”
低レベルの学生がやってくるので、叩きなおす、という雰囲気でしょうか。甘い学生に、「社会の厳しさを教えてやる」的な。
それに対して、反対派の方々は
と言った論を述べているようです。まあ、「自分が受けるならこんな研修は嫌だ」と思っている人がほとんどだと思う。
余談だが、最近話題の 村上春樹 著 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』にはこの手のセミナーに対する手厳しい批判が有り、村上春樹は自己啓発セミナーを嫌っているようである。
・・・さて、これ、どう考えればいいのだろう?
でも、よく考えると、これって昔からされている議論である。X理論とか、Y理論とかで。
X理論・・・人は本来怠け者。鞭打たないと働きません。という立場
Y理論・・・人は進んで働きたがる。自己実現を助けなさい。という立場
でも、我々は人間にはXの部分も、Yの部分もあることをすでに知っている。そんな人間は極端じゃない。したがって「時と場合によります」が正解なのだろう。
しかし、私は敢えて「新人研修」にスパルタ研修を用いることには賛同できないと言いたい。(賛同する人、ゴメンナサイ)
理由は2つある。
- 恐怖で人を従わせることは、倫理上正当化出来ない。たとえ結果として研修を受けた人が成長しようとも。
- 「スパルタ研修でもなんでも、若者に職が用意できるのはいいことだ」という人がいるが、結果が良ければプロセスはなんでも良い。というように聞こえる。人の成長はプロセスが本質であり、それを無視して企業の論理で「若者を調教」することは許されない。
もっと言えば、「あなたの子供をこの研修に行かせたいですか?」という問だ。
私は自分の子供をこのような場に送りたくない。王将の経営陣は、自分の子供をこの研修に行かせてもいいと皆思っているのだろうか。
そうであれば、信念にもとづいて行なっているのだ。批判は無視すればよい。
しかし、王将の経営陣が自分の子供をこのような研修に送ることを躊躇するならば、
「己の欲せざる所は人に施す勿れ」の原則に則るべきだと思うのだが。