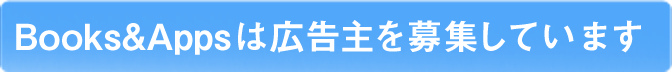コンピュータは単なる計算機で、電卓と同じです。従って、電気を使って計算をさせる機械といえます。もちろん、「表現力」がある機械なので、電卓とは使い勝手や見た目が大きく異なりますが、間違いなく単なる計算機です。
コンピュータは単なる計算機で、電卓と同じです。従って、電気を使って計算をさせる機械といえます。もちろん、「表現力」がある機械なので、電卓とは使い勝手や見た目が大きく異なりますが、間違いなく単なる計算機です。
繰り返しますが、電卓と同じです。
でも、ホームページを見たり、音楽を聞いたり、写真を編集したりできる。電卓とは違うじゃないか、という意見が多いと思います。
たしかにそうです。ですから、「表現力がある」という言葉を先ほど用いました。
「表現力がある」とはどういうことか。
電卓は、計算結果を数字でしか表せません。1+1の結果は2と表示されます。3+4の結果は7と表示されます。
でも、コンピュータは計算結果を「音」や「色」で表現する事もできるのです。そこが電卓との大きなちがいです。
例えばキラキラ星という曲、ピアノで演奏すると、ド・ド・ソ・ソ・ラ・ラ・ソ、と鍵盤を押して演奏します。
ここで、ドを数字の1、ソを数字の5、ラを数字の6と置き換えてみましょう。
キラキラ星の演奏は、1・1・5・5・6・6・5と表現ができます。当然ですね。
もし、電卓の1の数字を押すと、「ド」という音が出て、5の数字を押すと「ソ」の音が出て、6の数字を押すと「ラ」の音が出るようにすれば
電卓で演奏ができますね!データとして1・1・5・5・6・6・5というデータを持っておけば、いつでも演奏可能です。
コンピュータは音を数字に置き換えることによって、音楽を再生しているのです。
写真も一緒です。1を赤、2を青、3を緑と言った形で、数字を色に置き換えてしまえば、コンピュータは写真を扱うこともできます。
このように、数字に置き換え可能な情報であればコンピュータはそれを扱うことができます。
そして、「ド」を1、と言った形に
数字と音、数字と色などの置き換えをやってくれるものが「ソフトウェア」というものなのです。
この対応付けを専門用語で、「エンコード(符号化)」と言います。ね、簡単でしょう?